H17.6.21〜8.11
同館の期間限定公開「この一品」常設展示室1にあります。
7月31日午後1:30〜山田住職の松平忠輝公についての講話がありました。
 貞松院山田和雄住職のぎゃらりーとーく
貞松院山田和雄住職のぎゃらりーとーく続いて午後2:50〜尺八の演奏会がありました。
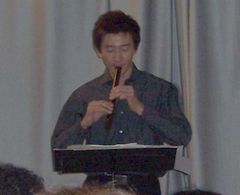 渡辺淳さんの演奏 一節切(ひとよぎり)尺八
渡辺淳さんの演奏 一節切(ひとよぎり)尺八「乃可勢」の笛 諏訪市博物館に展示中
H17.6.21〜8.11
同館の期間限定公開「この一品」常設展示室1にあります。
7月31日午後1:30〜山田住職の松平忠輝公についての講話がありました。
 貞松院山田和雄住職のぎゃらりーとーく
貞松院山田和雄住職のぎゃらりーとーく
続いて午後2:50〜尺八の演奏会がありました。
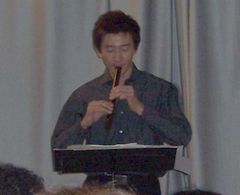 渡辺淳さんの演奏 一節切(ひとよぎり)尺八
渡辺淳さんの演奏 一節切(ひとよぎり)尺八
貞松院 ヒノキの塀
平成17年7月29日写す
あけが気づいてくれたのでさっそく撮ってきたよ。
ちょうど近所の人がいてヒノキの香りが通りに漂ってとても良い匂いだって。
本堂の屋根は今は落ち着いた色です。




貞松院訪問と御柱史跡行脚
平成16年5月1日(土)
念願の”野風の笛”と対面

改修が終った貞松院の屋根


枝垂桜は残った 忠輝公に花を捧げる

”乃可勢”と銘打ってありました。
裾には織田家家紋の金蒔絵。 一節切。 穴は表に4つ裏に1つ。
代々の天下人 信長・秀吉・家康に受け継がれ、忠輝公に渡されたもの。


右上の笛は”秋声”という。棗、茶碗と五郎八姫の杯 左は天海からの書簡 右は忠輝の自画讃

茶臼 忠輝は茶人でもあった。

山田和雄住職と記念撮影
| ▽貞松院に着いてまず忠輝公のお墓参りをさせていただく。ちょっとしおれていた菊の花を片付けて持参した花に替えさせていただいた。五月晴れの土曜日である。寺の中はひっそりと静かだった。 ▽あらかじめお願いしてあったため住職が忠輝公関連の本を携えて来られましたがなんと午前11時から午後1時までもお話をして下さって、お疲れではないかと気になるほどでした。(午後2時から法事があるとお聞きしていましたし、、。) ▽忠輝公の生きた時代背景、忠輝公の人間像、外国との繋がりもあり、友人も多かったなど、、。 ▽さて”野風の笛”は普段はお蔵にしまってあり、特別な時しか見せることは出来ないものだそうです。茶釜などの遺品は見せて いただけるということでした。私たちも茶釜だけでも見ることが出来れば嬉しいと思っていました。 ▽話が一段落すると住職が次の部屋の襖を開けて下さって促されるままに入ると卓袱台の上になんと”野風の笛”が置かれていたのです。それを見たときは3人とも鳥肌が立ちました。声も無くジーッと見つめた次第です。 ▽そもそも東京在住の淑江さんが宝塚歌劇団花組に元生徒さんが入団していて、昨年「野風の笛」を上演したのを見て、今回の 忠輝公のお墓参りが実現したのです。そんなことを事前の電話で説明しお願いしてありました。「宝塚さんにはお世話になったし 、ご縁を感じますから」と仰って特別見せて下さったようです。 ▽お籠の中にも入らせていただきました。「お籠に乗るのは決して楽なことではないですよ。揺られて酔うし、狭くて窮屈な思いをしたようです」と。そういえば−籠の中の鶏−は窮屈なイメージですね。確かに狭かったです。 ▽歴史に堪能な住職につられて信長・秀吉・家康の時代にタイムスリップした一時。本当にありがたい一時でした。 ▽これも色々な”ご縁”で実現したこと。400年の歴史を越えて忠輝公に会えたように感じました。 ▽本堂や枝垂桜のある中庭まで案内してくださり、すっかり貞松院ファンになりました。 ▽これからも時々お墓参りをさせていただこうと思います。 ▽昭和30年に発行され62年に復刻印刷された{諏訪忠輝会}編纂の「松平忠輝」という本を下さったので興味のある方は連絡下 さい。 |
| ▽さて貞松院を出ると五月晴れの中、3人で御柱行脚が始まる。下社の木落し坂を下から登る。頂上から下を見るとヒエ〜〜ッ!!ブルブル〜〜〜! 下りは林へ続いている小道を下りた次第。大勢の見物人 が来ていた。 ▽大平の棚木場まで行ってウグイスのさえずりと東俣川のせせらぎをおかずにお昼を食べ、尽きること無いおしゃべりが続いた。 ▽前宮へ行く道を間違えた(方向音痴約2人)おかげで上社の参道も見ることが出来た。 ▽いつもはひっそりと静かな前宮も明日の準備で大勢の人が集まっていた。 ▽御柱屋敷もしかり。川越し地点では夕方の風が寒くなってきた。日が伸びて日没を惜しむかのような人々に混じって3人とも満足の一日を感謝し帰路についた次第です。夕方6時半でした。 ▽ぎんちゃんとさっちゃんが急に用事で来られなくなり残念でした。 |





