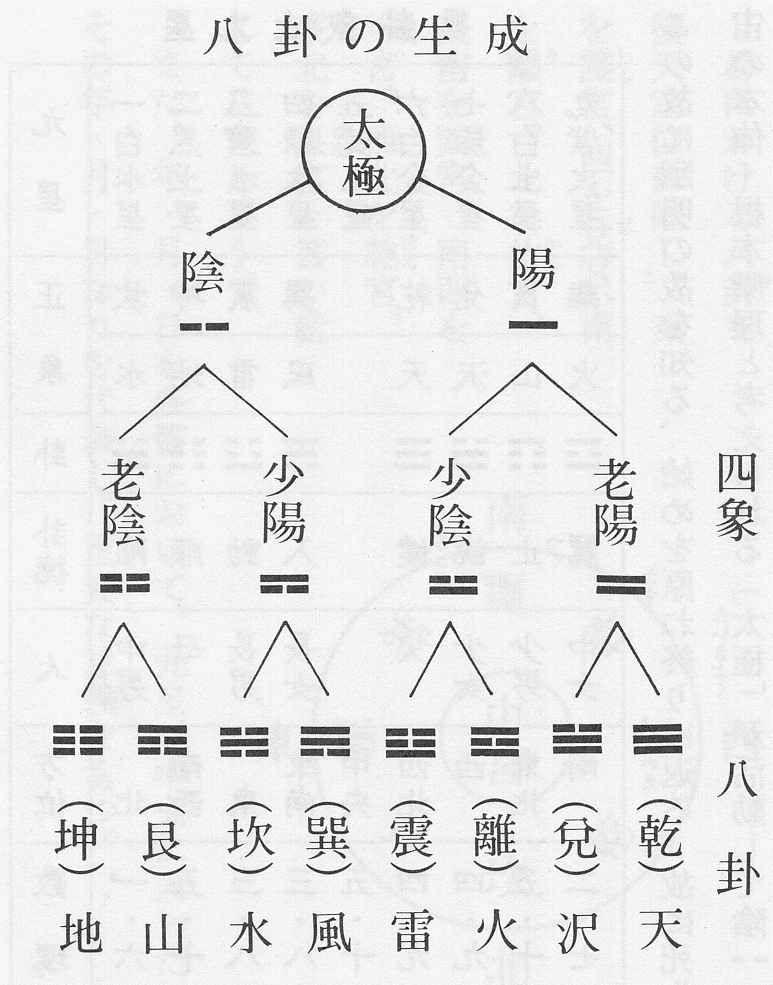
易について
易は、遠い昔、約5千年の前の古代中国で、伝説上の帝旺伏犠が、天地自然の万象を見て創ったものとされています。現代の色々な”占い”の大元となっていますが、実はこの―(陽)と‐ ‐(陰)からすべては始まっているのです。
易は、古代の帝旺伏犠が天地の万象を観察して、天地の理法に則り、陰陽の易理をハ卦に形象化したものに始まるといわれています
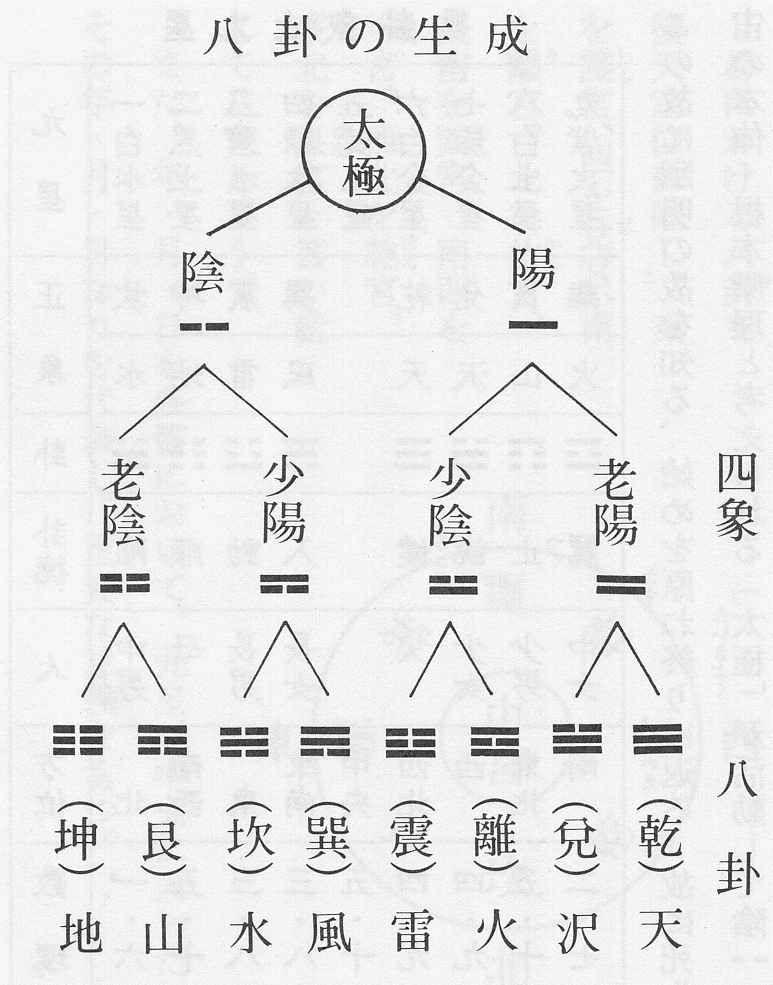
太極が陰と陽に分かれて、これが互いに組み合わさって、養老、小陰、小陽、老陽の4つの象を生じ、さらにそれが、天人地の三才に交わることによって八卦を生じたものです。
宇宙の万象には、陰と陽相対する2つの現象が存在する。しかもこの2つの根元は裏表の関係にあり全く別のものではなく、互いに相手によって表れる関係である。男・女、寒・暖、積極。消極、強・弱、大・小、上・下、内・外、右・左のように。男は陽、女は陰と相対しているが、性格から見れば男も女も、ともに積極的は陽、消極的は陰で表される。易では陽を―、陰を- -のしるしで表すが、これは文字ではなくシンボルで、このシンボルを爻という。思想を形で表したのは易の卓見である。
先天図
この八卦は、八つの方位を示していますが、この八卦から「八方破れとか」とか「八方塞がり」とか「八方丸損」の言葉が出ています。宋の時代の邵康節(ちょうこうせつ)という学者によって完成されたといわれています。この図は、陰陽の原理に基づいて上と下、高い低いという考え方を中心に作られています。天の気が地に向かって下降しまた、地の気が天に向かって上昇し、この両気が交わって万物が育成する原動力を示すものです。
後天図
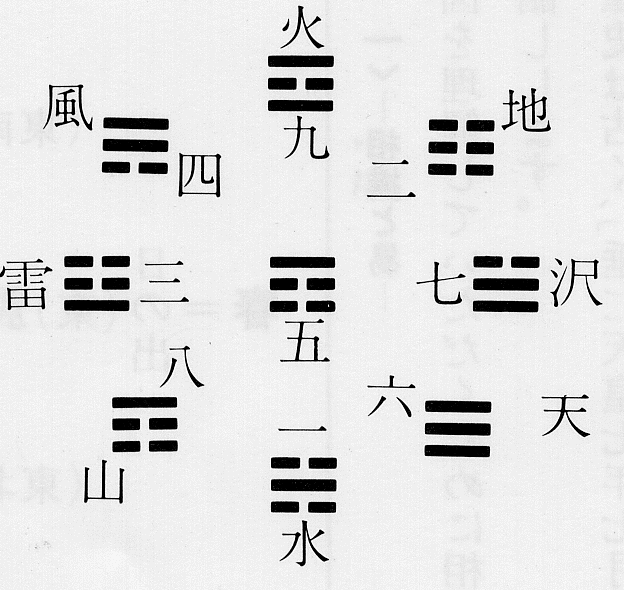 4千年程前、黄河の支流に洛水という河があり、ある年、洪水になりました。その時の王、中国の夏(か)の王=禹(う)がこの洪水を治めました。その時川の中から大きな亀が現れその背中に”魔方陣”と呼ばれる不思議な数字の模様があったといわれています。東・西・南・北・東北・東南・西北・西南の八方と中央の9つの地点に1から9までの数が並んでいました。これが洛書の後天上位といわれています。この後天上位の伝説は数と九星を神秘的に意義付けようとしたものでしょう。今、一般的に八卦と呼ば
れているのは、この後天図を示しています。
4千年程前、黄河の支流に洛水という河があり、ある年、洪水になりました。その時の王、中国の夏(か)の王=禹(う)がこの洪水を治めました。その時川の中から大きな亀が現れその背中に”魔方陣”と呼ばれる不思議な数字の模様があったといわれています。東・西・南・北・東北・東南・西北・西南の八方と中央の9つの地点に1から9までの数が並んでいました。これが洛書の後天上位といわれています。この後天上位の伝説は数と九星を神秘的に意義付けようとしたものでしょう。今、一般的に八卦と呼ば
れているのは、この後天図を示しています。
先天図が、上下・高低を中心にとらえているのに対し、後天図は、東西南北の考え方から、物事を平面的に捉えています。
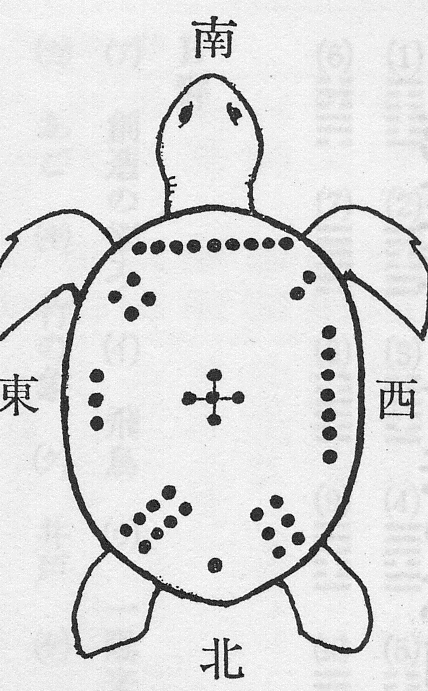 また、後天図は先天図のように陰陽の交じり合ったものとは見ずに、自然界を循環している気を取り上げ、気の循環としての易卦の変化を考えたものです。
また、後天図は先天図のように陰陽の交じり合ったものとは見ずに、自然界を循環している気を取り上げ、気の循環としての易卦の変化を考えたものです。
宇宙に気が循環することで、春夏秋冬・朝昼有夜の区別が生じ、人に気がめぐることにより運命の消長が生ずると考えるのです。
「万物は雲に出ず。震は東方なり。巽に斎う。巽は東南なり、斎とは万物の潔斎を言うのである。離は明なり。万物皆相あらわれる。南方の卦である。・・・艮は東北の卦である。万物の終りをなすところでまた始めをなすところである。故に艮に成艮す。」 説卦伝第5章
そして八卦が生成、発展、交流して六十四卦となったのです。
(十干一二支と5行説の起源)
中国では、天の数を五、地の数を六といっています。五からは十ができ、六から一二が生まれる事は考えられます。ですから、10干のことを天干といい、12支のことを地支とも言います。一般的に、10干は空間・天・陽を示し、12支は時間・地・陰を示しています。
易経の構成
中国儒教の根本経典である四書(大学・中庸・論語・孟子)五経(易経・書経。詩経。礼記・春秋)の中の1つである易経は、上経30卦と34卦の上下に分けられています。従って卦辞は64卦です。易経は経と伝の2つの部分から成り立っていて、経(卦辞)は64卦の形象の直接の説明です。伝は彖伝上下・象伝上下・繋辞伝上下・文言伝・説卦伝・序卦伝・雑卦伝の7種10篇からなり、孔子の作と伝えられ、十翼とも言います。十翼の翼は助けるという意味です。
繋時伝
易を素材として哲学的・思想的説明がされ、総論的な役目をしている。繋時伝の文の中には名言が多く後世に残る言葉が記されている。
彖伝・象伝
彖伝は卦辞についての解説であり、象伝は形象についての説明で、卦の全体に関するものを大象、1つの中の各文に関するものを小象といいます。十翼の中ではこの象伝の文章が古い作だと言われています。
説卦伝
卦の能力・形、八卦の詳しい説明があり、これから色々と演繹(えんやく)して象の説明におよんでいます。
文言伝
64卦の中で乾炒為天と坤為地について詳細しています。
序卦伝
64卦の配列順所を意味付けて説明してあります。変化・動的という点でとらえているので弁証法的な考え方が見られます。
雑卦伝
64卦をそれぞれ2つずつ組み合わせて1対にして、卦名の意味を対照的に説明したもので、実際に占う場合に役立つことが多くあります。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()